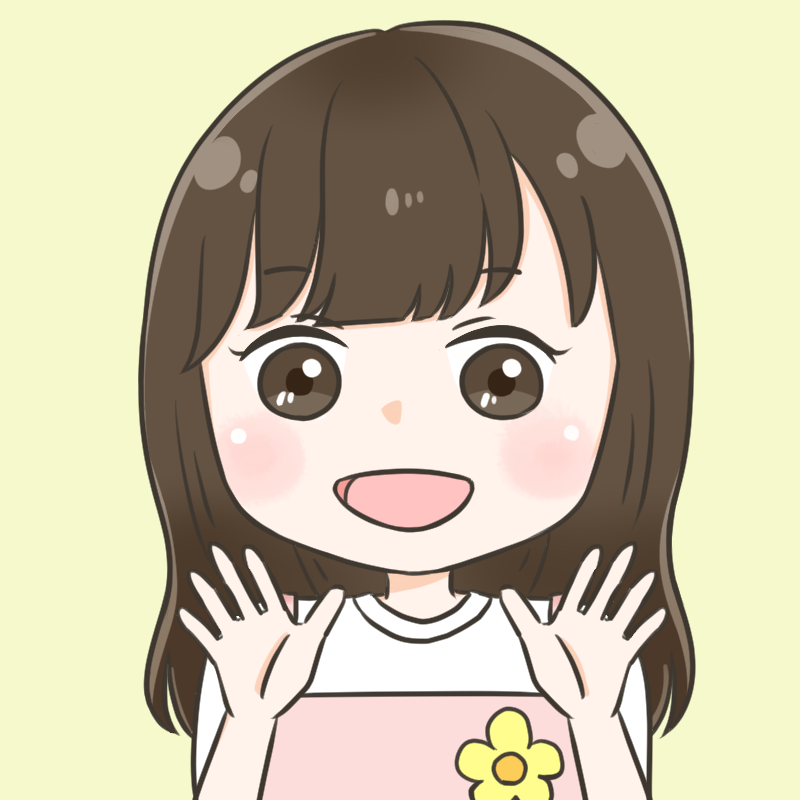どうも!保育士園長のまゆあです。
今回のテーマは「保育者の業務改善」についてです。
保育士や保育者が抱える業務は多く、大変です。
どうにか負担を軽減し、業務の改善を図ろうとしている保育園は多いと思います。
また、保育者さんの中には今すぐにでも改善してほしいと願っている方が多くいると思います。
こどもの最善の利益を考えなければならないのに、業務の負担が大きければ考える事もままなりません。
ですが、業務の負担軽減、改善がされれば、それだけ保育の事に時間を費やすことができるようになります。
記事では保育業務の負担を軽減し、改善する為のポイントを3つ紹介していきます。
こどもたちの為にも業務改善を図っていきましょう。
スポンサーリンク
保育業務は負担がとても大きい!
保育業務は大変な事も多く、内容も様々です。
大まかなものを挙げてみると
・保育書類作成 ・保護者対応
・行事の開催 ・職員の研修
・子育て支援 ・地域との連携
・園内外の整備、消毒
・安全管理 ・災害対策
上記の様な感じです。
ここから更に細分化されていきます。
こどもたちが安心して、安全に過ごせるようにする事は大前提の事。
更に保育の専門性を発揮しながらこどもたちにとって何が一番いいのか、最善の利益を追求しながら保育を行う事が求められます。
ところが保育園によってはサービス残業や人間関係、慢性的な人手不足など配置人数の問題を抱えている所もあり、保育の質の向上どころではなく、現状維持で精いっぱいの所も多いでしょう。
この様に保育園を取り巻く環境は大変なものがあり、その現場にいる保育者は大きな負担を抱えているのです。
スポンサーリンク
保育者の業務改善をする為のポイント
①やめる勇気を持ち、不要なものを無くす
まずは「やめる勇気を持つ」です。
やめる勇気とは?と疑問に思った方もいらっしゃるでしょう。
やめる勇気とは読んで字のごとくですが、今までやっていた事を無くす事。
要は「不要なものを無くす」という意味になります。
みなさんの保育園や職場はどうでしょうか。
何かをとりやめた経験はありますでしょうか。
私は保育の世界で生きてきて、業務が増える事はあっても、減る事があまり無いと感じていました。
何かあれば新たなルールができますし、子育て支援や地域との連携、選ばれる保育園作りなど、新たな業務が年々発生しています。
しかし、冷静になって考えてみると、実は無くてもいいものや、もっと効率よくできるやり方があったりものもあります。
例えば「行事」
保護者側からすると行事は嬉しいものですが、こどもの目線で考えると行事の取り組みに無理があることもあります。
また、「保育の中の行事」ではなく「行事の為の保育」になってしまう可能性もあります。
他には「壁面装飾」
確かにこども向けに作られた装飾はかわいいものも多いです。
しかし、それを毎回作るとなると負担は大きく、凝りだしたら止まりません。
どちらも「こどもの為」であると思いますが(ですよね?)、こどもたちは求めていないかもしれません。
・保育園でこれはやるべきだ
・これくらいやって当たり前
こんな感じで考えていると、やめるにやめられなくなってしまいます。
手っ取り早く改善をする為には無くすのが一番ですが、保護者の理解も必要になります。
何でもかんでも無くすという訳ではありませんが、こどもの目線に立って本当に必要か、必要だとしたらどのくらいの負担になっているかを常に検証して負担軽減、業務改善に繋げていきましょう。
スポンサーリンク
書類の簡素化
次は書類の簡素化です。
保育書類作成は保育業務の中でも負担が大きいものになります。
書類作成業務にかけられる時間が限られている中、各種指導案月案や個人案などを作成するのは大変な事です。
ただ、書類の中には作成しなくても良いものもあるはずです。
監査では各種書類の作成が求められていますが、簡素化しても意図と評価反省がしっかりと行えており、次に活かすことができれば監査上は問題ありません。
(自治体にも確認してみてください)
また、施設独自で作っているものがあるとしたら、本当に必要かどうかを定期的にチェックする必要があると思います。
書類関連ではICT化により書類作成をタブレットやパソコンなどで作成している園も増えてきています。
・フォーマットがすぐに用意できる
・印刷も可能
・予測変換で作業効率アップ
ICT化が進んだおかげで、手書きから切り替えた保育園も多いです。
アプリやパソコン上で書類を作成する事に抵抗がある方もいらっしゃいますが、慣れれば手書きよりも断然早いです。
簡素化した上で、さらなる作業効率の向上を目指せば負担も減っていきます。
スポンサーリンク
人材の確保と離職を防ぐ
最後は人材確保と離職を防ぐです。
すぐには解消できない事でもありますが、人材を十分に確保し、離職を防ぐことで業務の負担を軽くしていきます。
離職を防ぐ事ができれば、職員の在職年数を上げる事ができます。
毎年のように何人も新しい保育者が入職するような状況だと、一から教える事になりますよね。
もちろん必要な業務ではありますが、離職するような環境でなければそもそもその業務は発生しません。
また、職員全体の在職、経験年数が上がる事で連携を取りやすくなりますので、人材の確保と離職を防ぐ取り組みは大事になります。
スポンサーリンク
保育者の業務改善をすると働きやすい職場になる
保育者の業務を改善する事は、保育者の負担を減らすだけでなく、「働きやすい職場作り」にも繋がります。
働きやすい職場になれば人材も定着し、業務改善に向けた取り組みも行いやすくなります。
今回3つのポイントを紹介しましたが、業務改善、負担軽減については今後も考え続けなければならない問題だと思います。
国や自治体も業務改善、負担軽減を考え通知を発出していますが、動きは遅いです。
現場で日々保育している私たち自身が、そして園長をはじめ園全体で積極的に考えて取り組んでいきましょう。
スポンサーリンク
全てはこどもたちの為に
ここまで負担軽減について書いてきましたが、全てはこどもたちの為でもあります。
業務の負担が軽減されれば、こどもの事を考えたり、保育の質向上に向けた取り組みも行いやすくなります。
その結果、こどもたちが安心して保育園で過ごす事ができれば、保育園全体がいい雰囲気になっていきますし、何よりこどもも保育者も過ごしやすい環境になります。
全てはこどもたちの為。
保育者の負担軽減を図り、業務改善を進めていきましょう。
スポンサーリンク
*************
【読者の方へお知らせ】
この度、10年以上の園長経験を生かしたnoteをリリースいたしました!
タイトルは…
「園長歴10年以上の自信作!保育者が働きやすい保育園(職場)を作り上げる10の秘訣」
あなたの職場を働きやすい職場にするための秘訣を10個にまとめました!
園長先生や主任、リーダー保育士だけでなく、これから上の役職を目指!と思っている方にも参考になる内容となっております。
有料ではありますが、10年以上取り組んで成果があったものばかりですので、自信をもってお届けいたします。
noteの会員でXのアカウントをお持ちの方は割引になるサービスもあります。
noteをリリースいたしました!
お手に取っていただけたら嬉しいです。
この投稿をリポストするとお得に記事を読むことができます。園長歴10年以上の自信作!保育者が働きやすい保育園(職場)を作り上げる10の秘訣 | 保育士園長まゆあ @hoikushiencyo #note #保育 #保育士 https://t.co/9HkDaAo2FT
— 保育士園長まゆあ@保育者が幸せに働ける職場作りやります (@hoikushiencyo) May 12, 2024
(こちらのポストに詳細をつけています)
一つでも多くの保育園(職場)が働きやすい場所になるよう願っています!
【購入はこちら↓】