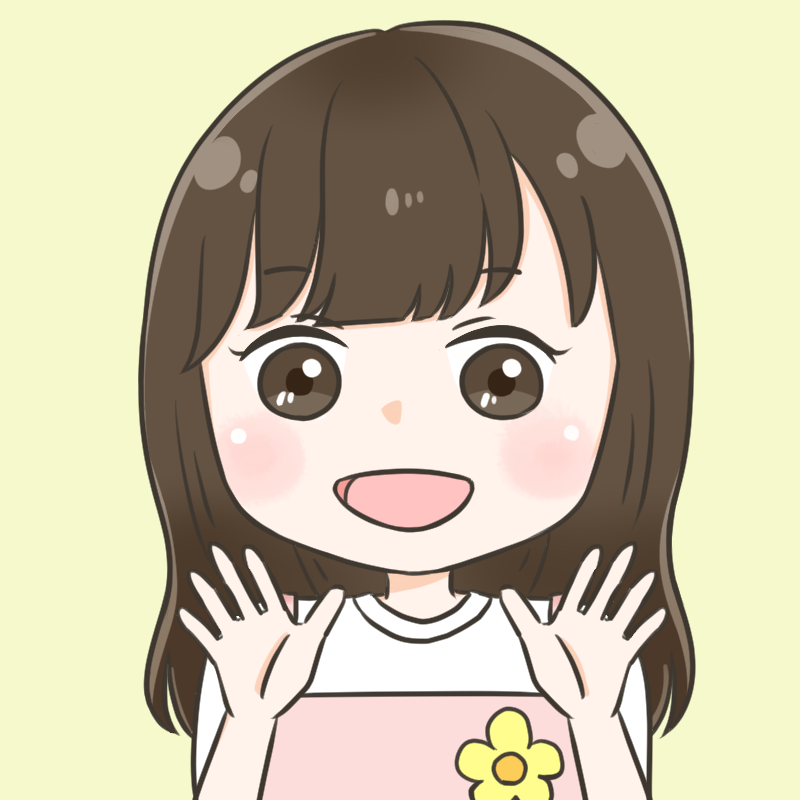どうも!保育士園長まゆあです。
今回は「こどもが片付ける力を身につける方法」です。
物を片付ける事は生きていくうえで大事な事です。
片付ける事が習慣化し、力が身につくと豊かな人生を歩むことも可能になります。
記事ではこどもが片づける力を身につける為の方法を6つ紹介します。
小さいうちからじっくりと取り組んでいき、力を身につけるように取り組んでみましょう。
スポンサーリンク
片付ける力は生きる上で大事な事

片付ける力は人間が生きる上で大事な事です。
片づける力を身につける事で
・物事を考える力(思考力)向上に繋がる
・時間の省略化が図れる
・仕分けや優先順位をつける力が上がる
この様な力が付き、人生をより豊かに送れることにもなります。
逆に身につかなかったら逆の事が起こりうることになります。
ですので、片付ける力を身につける事は大事な事なのです。
片付ける力は小さいうちから取り組んでいくと身につきやすいです。
すぐに身につけられるものではありませんので、長い目で取り組んでいく必要があります。
では片付ける力を身につけるためにどんな取り組みをすれば良いのでしょうか?
スポンサーリンク
①一つでも片付けたら「ほめる」

まずはこれを必ずやって欲しいのですが、片付けたら褒めてあげましょう。
こどもは大好きな人に褒められたらうれしく感じます。
褒められると「次もやろう!」という気持ちになり、片付けに対する意欲に繋がります。
そして、また片づけをした時に褒める、この繰り返しです。
その時に大事な事があります。
それは「一つでも片付けたら褒める」です。
褒めるのは全部片づけてから、と考える方もいると思いますが、小さいうちは全て片付けるだけでも大変な事です。
ですのでハードルをぐっと下げて「一つでも片付けたら褒める」。
これを意識していきましょう。
力をつけるには何事も「繰り返し行う」事が必要になります。
繰り返すことで物事に慣れていき、身につけられる様にしてみてくださいね。
スポンサーリンク
②大人と一緒に片付ける
こどもが小さいうちは大人の方と一緒に片づけを行ってみましょう。
片付け自体は大変なものという認識を持つ子も多いです。
(大人でもそうだと思います)
そこで、大人と一緒に片づけをする事で、こどもが感じる大変さを和らげてあげるのです。
見守る大人側からしてみたら、こども自身の力でやってほしいという気持ちもあると思いますが、先ほども書いた通り、こども側からしたら片付けることはとても大変なことでもあります。
大人と一緒に片付けることで取り掛かりやすくなり、繰り返すことで力を身に付けることもできるようになります。
ぜひ、一緒に楽しみながら片づけを行ってみてください。
スポンサーリンク
③完璧に片付けなくても良い
片づけを行う際に、全てのものをしっかりと所定の場所に片付けるまで行う事が多いと思います。
最終的にはそうであってほしい所ですが、初めから完璧に行う事は難しいです。
ですので完璧さを求めないようにしてみるのも一つの方法です。
・一つの箱(場所)にしまうだけでOK
・まずはひとつ片付けるだけでOK
こんな感じで完璧ではなく何かやったらOKくらいの感覚で取り組んでみましょう。
完璧さを求めてしまうとつまらなくなったり、息詰まる感じがしてしまい、大人もこどもも辛くなってしまう可能性があります。
大人でも完璧な方は少ないと思います。
完璧さを求めず、気楽に取り組んでくださいね。
スポンサーリンク
④片付ける場所を分かりやすくする
おもちゃなどを出してもどこに片付ければいいのかわからない、わかりづらい状態では片づけを習慣づけることは難しいです。
ですので、片付ける場所は分かりやすくする事を意識してみましょう。
写真や絵を用いると場所が分かりやすいですし、入れ物なども余裕ある大きさにする事で中に何が入っているのか分かりやすくなります。
片付けを容易にする為、「視覚的な分かりやすさ」を意識してみてくださいね。
スポンサーリンク
⑤ゲーム感覚で片付ける
こどもはゲームが大好きです。
お友だちとのやりとりでも姿が見られることがありますが、競い合って勝ったら喜んで負けたら悔しがってといった姿はよく見ると思います。
片づける力をつける為には「片付け自体を行う」事が必要。
片付けの経験を積んでいけば力はついていきます。
その取っ掛かりとしてゲームで取り入れるというのは有効な手段でもあります。
大人も一緒に楽しんでみてくださいね!
スポンサーリンク
⑥片付ける理由を伝える
これは言葉を話せるようになったり、意味を理解できるようになってからの話になりますが、片づけをする理由を伝えてみましょう。
こどもも大人もそうですが、納得できた事は自分が行動する理由になります。
片づけをする事で
・物を無くさないで済む
・踏んで壊れる事が無くなる
片付けの理由は様々ですが、こども自身が納得する事ができれば片付けに興味が向くようになります。
こども自身が必要だと思って取り組むのが一番ですが、すぐには難しい所。
じっくりと時間をかけて伝えていきたいですね。
スポンサーリンク
こどもが安心して取り組むために

片付ける力を身につける為の方法を6つ紹介しましたが、こどもが安心して物事に取り組む為には安心感も必要です。
小さいうちはもとより、年齢を重ねても安全基地となる存在があってこそ力を身につけ発揮していきます。
ですので、大人側から安心感を与えられる様な関わりが重要になってきます。
・片付けたら「ありがとう」の言葉をかける
・感謝の言葉と、時には抱きしめてあげる
片づけはこども任せにする、怒って片付けさせるのではなく、大人も一緒になって取り組み、こどもが安心して片づけを行える環境を作っていきましょう。
スポンサーリンク
*************
【読者の方へお知らせ】
この度、10年以上の園長経験を生かしたnoteをリリースいたしました!
タイトルは…
「園長歴10年以上の自信作!保育者が働きやすい保育園(職場)を作り上げる10の秘訣」
あなたの職場を働きやすい職場にするための秘訣を10個にまとめました!
園長先生や主任、リーダー保育士だけでなく、これから上の役職を目指!と思っている方にも参考になる内容となっております。
有料ではありますが、10年以上取り組んで成果があったものばかりですので、自信をもってお届けいたします。
noteの会員でXのアカウントをお持ちの方は割引になるサービスもあります。
noteをリリースいたしました!
お手に取っていただけたら嬉しいです。
この投稿をリポストするとお得に記事を読むことができます。園長歴10年以上の自信作!保育者が働きやすい保育園(職場)を作り上げる10の秘訣 | 保育士園長まゆあ @hoikushiencyo #note #保育 #保育士 https://t.co/9HkDaAo2FT
— 保育士園長まゆあ@保育者が幸せに働ける職場作りやります (@hoikushiencyo) May 12, 2024
(こちらのポストに詳細をつけています)
一つでも多くの保育園(職場)が働きやすい場所になるよう願っています!
【購入はこちら↓】