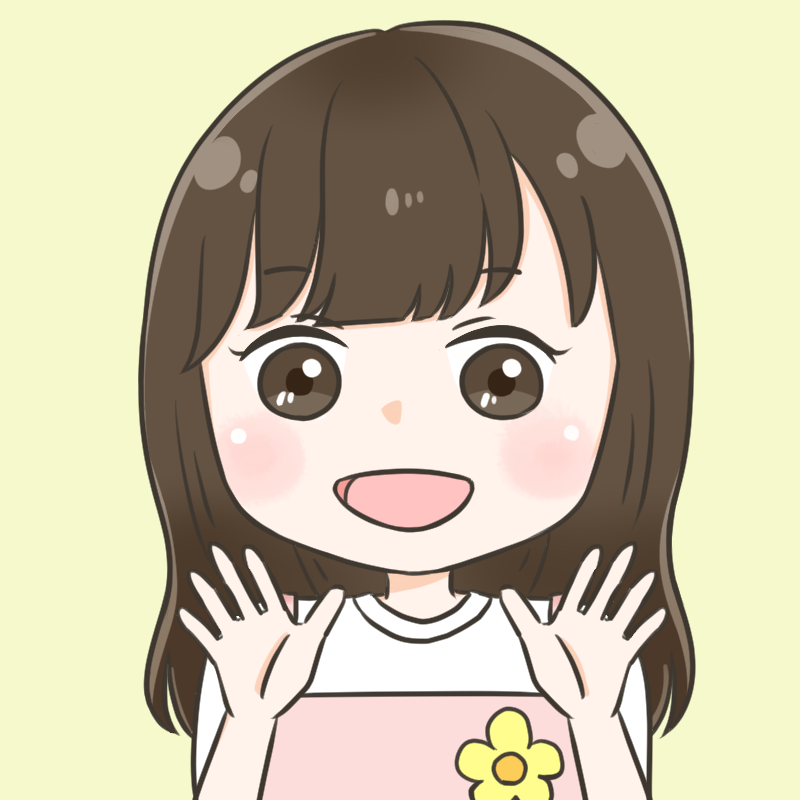どうも!保育士園長のまゆあです。
今回のテーマは「こどもの自己肯定感」についてです。
・子どもの自己肯定感が低くないか心配
といった方向けへの記事になります。
あなたは「自己肯定感」という言葉をご存知ですか?
自己肯定感とは自分の事を大切にしたり肯定できる力の事で、豊かな人生を歩むためにも必要な力とも言われています。
この自己肯定感が高いか低いかでその人の印象や人生が変わってきます。
自己肯定感の違いが子どもでも見られたりするので、
小さいときから自己肯定感を高める取り組みをすることは良いことでもあります。
今回はこどもの自己肯定感を高める為の方法を4つ紹介します。
こどもがより良く生きていけるように、ぜひ取り組んでみてください。
スポンサーリンク
最近よく聞く自己肯定感とは?

さて、あなたは自己肯定感とはどういった力の事を指すかご存じですか?
冒頭でもお伝えしましたが、自己肯定感とは
この様な力を指します。
自分をありのままに受け入れ、認め、他人から何を言われてもゆるぎなく自分を信頼できる力はまさに生きていくうえで大事な力になります。
あくまでも感覚的な力なので、数値化したりする事はできませんし、何が正しいのかと言う事をはっきり言う事も難しいです。
ですので、高いから良い、低いから悪いという話ではありません。
しかし、自己肯定感が高い・低いがその人の人生を大きく左右することもあり得るので、高めておきたい力である事は間違いないです。
そして、自己肯定感は周りの大人との関わり合いで左右されやすいので、こどもと接する時は意識しておきたいものでもあるのです。
スポンサーリンク
自己肯定感が低いと将来にも影響が出る
では、自己肯定感が低いとこどもにどういった影響があるのでしょうか。
・自信が無く、積極性が無い
・物事をおこなっていても諦めてしまいがち
・お友達との関わり合いが苦手である
・不安げな表情を見せる事が多いなどの特徴が見られます。
大人でもそうだと思いますが、こういった特徴が見られる人は暗く見えたり、何を考えているのか分からなかったり、消極的に見られると思います。
大きくなると受験や就職など、社会を相手にする機会が多くなります。
消極的なのが悪いというわけではありませんが、まだまだ見た目や印象が大事な時代であることは間違いありません。
自己肯定感は社会を生きるためにも必要な力であることを覚えておきたいですね。
スポンサーリンク
自己肯定感を低下させる声掛けがある
あなたが普段使っている言葉がこどもの自己肯定感を低くする?
「○○くん、××しちゃだめでしょ!」
「□□ちゃんはちゃんとやっているよ」
「なんでできないの!?」 などなど
いずれもよく聞く言葉だと思いませんか?
実は、こういった言葉がけは子どもの「自己肯定感」が低くなってしまう可能性があります。
なぜ低下させるのかを次で解説します。
否定はこどもを委縮させてしまう
では、先ほどの例について解説していきます。
・「○○くん、××しちゃだめでしょ!」
↓
これは、「だめ」という否定の言葉かけになってしまいます。
ダメと言われ続ける事で、こどもは自然と「自分はダメな人なんだな」と思うようになってしまいます。
自分はダメな人と思ってしまうと自己評価が低くなってしまいます。
壁にぶつかったときも「自分はダメだからできないんだ」と諦めてしまうようにもなります。
更には、ダメという相手を信用できなくなってしまうので、人間関係を築く事が難しくなります。
この様に否定され続けると委縮してしまい、自己肯定感が低いこどもになってしまうのです。
スポンサーリンク
比較されることで劣等感を感じてしまう
・「□□ちゃんはちゃんとやっているよ」
↓
お友達やきょうだいとの比較は劣等感を感じる原因になります。
きょうだいや友だちと比べてしまう事も自己肯定感を下げる原因になります。
「信頼する大人が自分より他の人の方がちゃんとしていると言っている。」
「自分だって頑張っているのに分かってくれない。」
比べる事でこどもはこんな気持ちを抱きます。
そうなると自分は友だちより劣っている、あの子より頑張るなんて無理だといった劣等感を感じてしまう事に繋がってしまいます。
結果として自己肯定感を下げてしまうのです。
できない事に目を向けてしまう声掛け
・「なんでできないの?」
↓
「できた事」よりも「できない事」に目を向けるようになります。
なんでできないの?と言われても、こどもにも理由があります。
また、こどもは成長段階にあるので、できない事があってもおかしくありません。
できない事ばかり言われると、自分の欠点ばかりに目が行きがちになります。
「またできなかったなぁ」という思考回路になってしまい、自己肯定感の低下を招いてしまうのです。
本当はできるようになった事も多いはず。
良い面を感じられる様な声掛けをしていきたいですね。
スポンサーリンク
自己肯定感を高める方法は?
①一番大切なのは「具体的に認め、ほめてあげること」
自己肯定感を育む為に一番大切なのは、具体的に物事を認めてあげることです。
認めるという事は、その事実を受け入れる事です。
親や保育士が認めてあげると受け入れてもらえたと子どもは感じ、安心感や次への意欲にもなります。
また、認めると同時にほめてあげることも大切です。
人間、ほめられると「また頑張ろう!」という気持ちになりやすくなります。
その結果が自分で道を切り開く意欲に繋がり、自己肯定感も増す事になります。
ここで大事なのは「具体的に」というところ。
ただ単に「すごいね!」といったほめ方だと何がすごかったのかが分かりません。
「○○が良かった」「××を頑張ったんだね!」など、あいまいな言い方ではなく具体的に言う事で認められた事実を受け入れる事ができるのです。
②こどもを励まし、勇気づける
あなたが何か物事を行う時、背中を押してくれる存在があると心強いですよね?
こどもも同じで、励まされながら物事に取り組むと、勇気をもって行おうとします。
今まで困難だったことも、勇気づけられることで乗り越えられるかもしれません。
「頑張ったね」「よくできたね」、こんな声をかけられたらこどもは嬉しくなります。
励ましや勇気づけは自己肯定感の向上に非常に有効なものです。
そして、それを行うのに身近な大人である保育者や保護者の方なのです。
こどもが前向きな気持ちになれるように、背中をそっと押してあげられる様に関わっていきましょう。
スポンサーリンク
③進歩できているという実感を与える
こども自身が以前より成長出来ているという実感を感じられると、自分自身の力をより信じることができます。
例えば、100点満点のテストで50点を取ってきたとします。
すると、保護者によっては「50点しか取れなかったの!?」「もっと勉強しなきゃね」などと言う方もいます。
ですが、そのように言うのではなく、50点取れた事をまずはほめてあげ、次にもう少し点を取る為にどうしたら良いかを一緒に考えます。
そして、次のテストで50点以上取る事ができれば進歩できたことをまたほめてあげるのです。
今回は例としてテストを挙げましたが、スポーツでもなんでも同じ事が言えると思います。
できなかったことに直面した時、子どもながらに悔しい思いをしたり、諦めてしまうような時もあるかもしれません。
ですが、それを乗り越えて物事を達成した時は嬉しい気持ちで満ち溢れると思います。
時には何回も「○○できたんだよ!」と言うかもしれません。
ほめる事もしながら進歩したことも実感できるように接していきましょう。
④叱る時はまずは気持ちを受け止め、具体的に伝える
時には叱る事も必要な時があるでしょう。
その時はまず気持ちを受け止めてあげます。
「△△したかったのかな」 などなど
泣いてしまっている事もあると思いますが、
気持ちを受け止めてあげるとこどもは安心感を覚えます。
安心するとこちらの言葉も聞いてくれるようになるので、
そこで良くなかった点などを伝えていきます。
言葉が理解できるくらいの年齢だと、伝える時も何が良くなかったか、どの様にすれば良かったのかなどを具体的に伝えることで子ども自身も直すべき点が分かります。
スポンサーリンク
自己肯定感が高いこどもはどんな成長を遂げる?
自分自身の事を大切し、信じる事ができる

自己肯定感が高いと、自分自身の事を大切にすることができます。
自分の事を大切にし、力を信じることで、生きる気力になったりモチベーションの増加にもつながります。
気力やモチベーションは何かを行動する際に必要な力です。
低いと生きる気力がなくなり、最悪の場合は死につながる事もあります。
自己肯定感の高さが、自身の命を守る事にもつながっていくのです。
積極的に物事に取り組める
積極的に物事を取り組むようになるのも自己肯定感が高い人の特徴です。
何事においても積極性を見せる事で、挑戦する機会が自然と多くなります。
沢山の事を経験できるのでおのずと経験値もあがり、さらなる自信を生むことができます。
スポンサーリンク
人生を前向きに歩んでいけるようになる
自己肯定感が高い人ほど、人生に対して前向きになる事ができます。
物事を積極的に取り組んでいける為、成功することも多くなるでしょう。
そうして成功体験を積むと何事も前向きに捉え、より積極的になっていきます。
失敗しても再度トライできるようになる
最近のこどもはすぐに諦めてしまうというような話があります。
ですが、自己肯定感が高いと、何かにつまずいてしまっても諦めずにまた挑戦しようとします。
再挑戦することで、成功する確率も高まりますし、成功した事実が更なる自信に繋がる結果になるのです。
大人は何かを再トライするときに、相当な労力やモチベーションを使うと思います。
こどもの時から再トライする事が当たり前のようにできていると、大人になって壁にぶつかったり失敗しても諦めずにいられるようになるのです。
スポンサーリンク
保育者、親自身の自己肯定感も高めよう
こどもに対しての自己肯定感を高める方法はお分かりいただけたかと思います。
では、接する側の大人=あなたは自己肯定感が高いでしょうか?
こどもの自己肯定感を育てていくためには、周りの大人の自己肯定感も高める必要もあるのです。
大人が自信を持てないと子どもも自信を持てない
自信を持って物事を行っている人と、自信がなさそうに物事を行っている人を比べた場合、どちらの人の方が信頼できると思いますか?
恐らくほとんどの人が自信を持っている人の方が信頼できると思うのではないでしょうか。
子育てや保育も同じで、接する側の大人が自信がないと子どもはそれを見透かします。
こどもによっては信頼できない、不安を覚えるなどの感覚になり、自信が持ちづらくなってしまいます。
大人も子どもも自己肯定感を高める方法は一緒
これまでこどもの自己肯定感を高める為の取り組みを紹介しましたが、それが大人であっても一緒の効果を得られます。
私も以前は自己評価が低く、どこか他人と比べてしまう自分がいました。
特に保育士になりたての頃は、同期にできる人が多かったので、不器用な私はリーダーや行事担当をいつまでたっても任せてもらえない時期が長かったです。
正直、職場に行くのが辛い時期もありました。
ですが、それでもちょっとずつできる事も増え、少しずつ自信が付いてくると任される事も増え、自然と一人でいろいろな事を行えるようになりました。
周りの人の励ましや応援があったのは言うまでもありません。
私の経験談ですが、ほめられ、認められると自然と自己肯定感が高まりますし、仕事のパフォーマンスもあがります。
それが今の園長業務にも活かされていると感じています。
保育士として自信をつけるなら自己肯定感を高めよう【成功と成長】もご覧ください
スポンサーリンク
何事もプラスに考えられるように

私が新人の頃、当時の園長先生からよく「保育は加点法だよ」と教えられてきました。
当時は言っている意味が理解できなかったのですが、保育者として経験を積んでいくと、こども自身がプラスに考えていける力や感じ方、子どもに何かをプラスしていくという意識の大切さを感じるようになりました。
それによって保育内容もどんどん変わりましたし、声掛けや接し方も意識して行うようになりました。
子育てを始めたばかりの方や、保育者として子どもに接している方は、こどもに対して励ましの言葉をかけたり勇気づけながら、その子の頑張りを認めてほめてあげましょう。
きっと、自己肯定感が高いこどもになっていきますよ!
そして、こどもたちがより良く生きられる様にサポートしていきましょう。