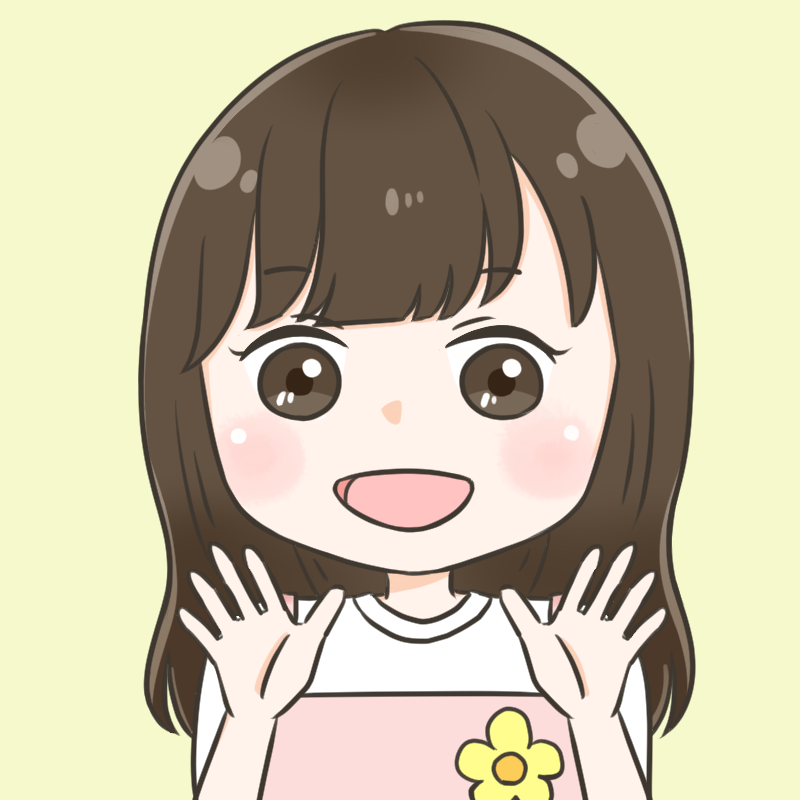どうも!保育士園長のまゆあです。
今回のテーマは「子育て支援」についてです。
保育園における子育て支援の重要性は年々増しています。
2018年に改定された保育所保育指針で「子育て支援」という言葉に改められており、従来の保護者に対する支援から形を変えました。
今後は子育て支援について、それぞれの保育園で考えていかなければなりません。
そして支援するにあたって保護者だけではなく地域との関わりも重要になってきます。
さて、そんな子育て支援ですが、経験が浅い保育者さんの中には「何をしていけば良いのか分からないよ」という方がいらっしゃると思います。
子育て支援に必要な力はいくつかありますが、その中でも私は「想像力」と「共感力」が大事だと思っています。
この2つの力が上がれば、おのずと子育て支援の質も上がっていくはずです。
今回はこの子育て支援力を上げる為に必要な2つの力についてお話ししていきます。
スポンサーリンク
保育園における子育て支援は年々重要に
年々重要になっている子育て支援。
2018年に改正された保育所保育指針の中では、第4章に登場します。
従来の保護者に対する支援から形を変え、「子育て支援」としてより広義な意味を持つようになりました。
子どもの最善の利益の保証を前提としつつ、保育園としては保育を行う中で保護者に対する支援をどのように行っていくのか、また、どのように連携して支援を行っていくのかを考えていかなくてはなりません。
保育園では子どもたちが毎日来るからこそできる事があると思います。
支援は途切れ途切れで行うものではなく、継続して行うのが理想ですからね。
そもそも、保育園には保育士、栄養士、看護師など、専門性の高い資格を持った人が働いていますよね。
それぞれが専門性をフルに発揮することで、保護者が安心して支援を受けられるようになるはずです。
子育てを取り巻く環境は日々変化しています。
保護者は変化が激しい中で子育てを行っていますので、そういった状況を理解しながら寄り添うような形で支援を行っていきたいものです。
スポンサーリンク
保育園は地域の子育て支援施設としての機能を持つように
また、今までは園に通っている保護者への支援が重視されていましたが、今後は地域で子育てしている家庭への支援も重要視されてきます。
例えば
・育児不安を抱える方の相談を受ける
・季節の行事への参加
・給食、離乳食体験
こういった活動を行っている保育園は多いと思います。
特に認可保育所では事業として子育て支援を行っている所は多いでしょう。
ゆくゆく入園したい保護者だったり、子育てしていて友だちを作りたいといった方、悩んでいて相談したい方などが利用しています。
私の園でも自治体の事業の一つとして子育て支援事業を行っており、在園児と一緒に遊ぶ機会や季節の行事に参加してもらうなどの子育て定期的に開催をしています。
この様に、こどもを預けている保護者だけでなく、「地域の子育て拠点施設」としての機能が求められているのです。
スポンサーリンク
子育て支援を行う時に必要な「想像力」と「共感力」
さて、子育て支援を行う際に必要な力は何でしょうか。
色々な意見があると思いますが、私は「想像力」と「共感力」がとても大事なのではないかと思います。
相手の状況を想像する事
相手の想いに共感する事
どちらも子育て支援に必要な力ではないでしょうか。
ベテランの先生であれば今までの経験から、ある程度の子育て支援を行うことは可能だと思います。
一方、経験が浅い先生が子育て支援を行うときに、何をすればいいのか見当がつかない事も多いでしょう。
私も新人時代にやってと言われたら、できる自信はありません。
何をやっても慌てていましたから(笑)
でも今思えば想像する力と共感する力があったら少しは違ったのかなとも思っています。
この2つの力を上げていく事が、子育て支援力を上げるポイントになっていきます。
スポンサーリンク
保護者の状況を「想像する力」

相手の背景を想像すること
保護者にあった支援を考えるのであれば、まずは想像することが必要です。
・どういった情報を得ている可能性があるか
・家庭でどんな対応をしたか
・どんな想いをもって子育てしているか
・どのような状況に置かれているか
色々と想像してみましょう。
考える時は具体的な支援策まで考えられると良いですね。
もちろん想像するだけでは支援は行えません。
しかし、いざ子育て支援を行うとなった時に準備ができているのとそうでないのとでは取り組み方が違ってくると思います。
背景を想像する事は、実際に子育て支援を行う際に有効な手段になります。
手に入れやすい情報は保護者を困らせることも
経験が浅いうちは、子育てに関する本や他の方の体験談などを読んで悩みの解決を図ることがあります。
私も新人のころは本を参考にすることが多かったです。
ここで一つ覚えておきたい事は「自分が手に入れられる情報は保護者も手に入れられる」ということです。
保護者は悩みを解決するためにいろいろな情報を得ようとします。
特に今はネットが発達しているので、子育てのノウハウから個人の体験談まで幅広い情報を入手できます。
つまり、保育者も保護者も同じ情報を得ることができるのです。
ですので、相談しようとして帰ってきた答えが、保護者自身も調べた事ばかりだったらがっかりしてしまう方もいると思います。
「違った答えが欲しかったのに…」
こういう風に思われてしまうのも想像できますよね。
もちろん、知識を得るために沢山の勉強をするのは悪いことではありません。
引き出しを増やしていくというのはどんなことでも大事な事です。
また、仮に保護者が知っていた事や試した事であっても、相手の背中を押すという意味では良い事でもあります。
ただ、自身が手に入れやすかった情報が、かえって保護者を困らせてしまう事もあるという事は頭の片隅においておきましょう。
想像力を高めるには?
想像力を高める取り組みとして有効なのが「ペルソナを作ってみること」です。
ペルソナとは本来マーケティング業界で使われる言葉。
詳細な設定をした架空の人物像を作り、その人物に合った商品やサービスを作り上げていくというものです。
これを保育園に当てはめると子育てしている方の状況を詳細まで決めて、その人がどんなことを求めているのかを考え、支援策を決めていくというやり方になります。
想像をめぐらしていくと、様々な考えが浮かびます。
正解か不正解かはここでは関係ありません。
その考えの一つ一つが、どれも自身の大事な引き出しになっていきます。
どの家庭であっても同じ支援とはならないはずですからね。
繰り返しペルソナ相手に想像する事で、子育て支援に必要な想像力が飛躍的に上げられることでしょう。
スポンサーリンク
保護者に「共感する力」をつける

共感は信頼への第一歩
子育て支援を行う時は様々な話を聞く機会があると思います。
そこで相手の話をさえぎらず聞き役に徹し、相手の話に共感する姿勢を持ちます。
共感する事は信頼関係を築く第一歩です。
話に真剣に耳を傾け、相手に寄り添っていく中で「この先生なら話を聞いてもらえるかな」、「ちょっと相談しようかな」と思える関係を作っていくのです。
実際に話を聞くと保護者の状況が見えてきます。
中にはあまり知られたくないことを相談する方もいるかもしれません。
話しにくいことを話してくれるようになる決め手が「信頼関係」なのです。
不安に思わない人に相談したいと思うのが普通ではないでしょうか。
信頼関係は子育て支援には欠かせないものと言う風にも言えますね。
共感力を上げる為に必要な事は
まず、共感力を上げるには相手を思いやる気持ちが大事です。
相手が何を考え、どういった支援を求めているのか、どんな気持ちだったのか汲み取っていく必要があります。
思いやる気持ちがないと、相手の気持ちに沿った支援が行えません。
自分の考えや気持ちではなく、相手の事を真剣に考えていきましょう。
また、よく観察する事も必要でしょう。
観察するというと、まじまじと見てしまうイメージを抱く方もいると思いますが、そうではなく、相手の雰囲気や話し方から気持ちを推察したり、表情を見て感じ取ったりと様々です。
よく見てよく考えてよく感じとる。
相手と同じ気持ちになれるように意識してみると良いと思います。
スポンサーリンク
保護者が自分で決められるように
子育て支援は「あくまでも支援」です。
保護者の代わりにそのことを行うのではありません。
保育者は色々な支援策を考えたり、提案したりと試行錯誤すると思いますが、最終的に決めて行うのは「保護者自身」です。
最終的には相手を見守るような感覚になるでしょう。
この辺は援助と支援の関係にも近いところがありますね。
見守るだけでなく、保護者が決めて行った結果がどうだったか聞くなど、フォローを入れることも忘れてはいけないポイントです。
もし、上手くいかない事があればまた一緒に考えたり提案したりします。
点ではなく線で考え、途切れの無い子育て支援が行えると、より関係性が深まっていくのではないでしょうか。
スポンサーリンク
想像と共感を忘れずに支援していこう

相手を想像し、気持ちに共感し、信頼関係を築きながら、保護者自身が自分の意思で決定していく過程を連続して支援する。
子育て支援は重要な事である反面、保育者としては難しく感じられる面もあります。
相手あってこその支援ですし、その相手は物ではなく気持ちを持った人間です。適当に支援を行うといった事が無い様にしないといけません。
まずは沢山想像することと、寄り添う様に共感すること。
この2つを忘れないで子育て支援をしていきたいですね。
スポンサーリンク