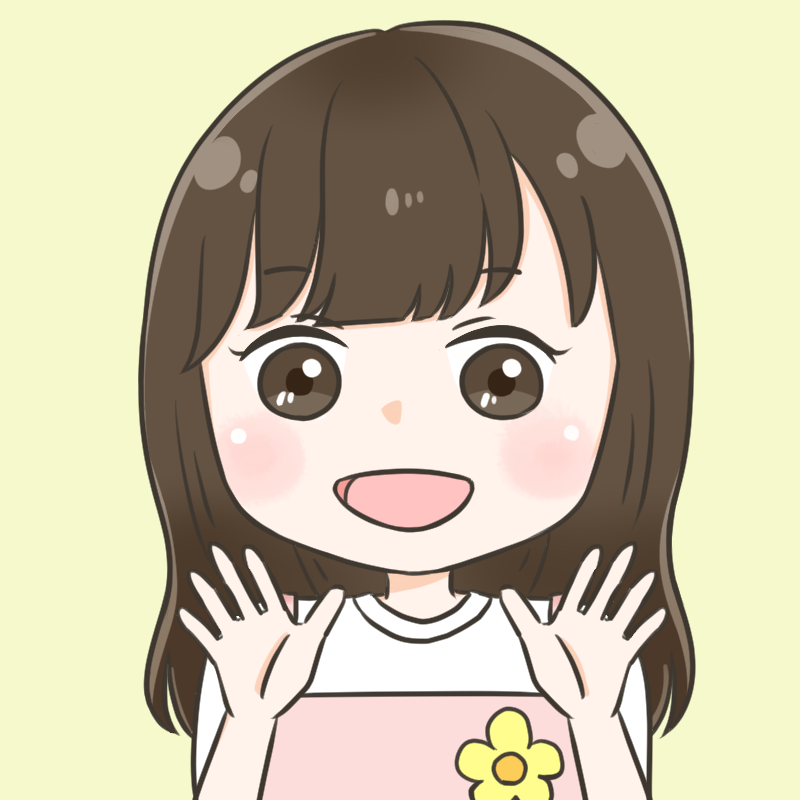どうも!保育士園長まゆあです。
今回は慣らし保育が終わった直後に気を付けたいポイントについて書いていきます。
新年度が始まると、新しく入園した園児の慣らし保育が行われます。
保育園では概ね2週間ほど慣らし保育の期間を設けている所が多いかと思います。
慣れない環境で泣いてしまうこどもも多くいますが、少しずつ環境に慣れてくると自然と遊び始めることがほとんどです。
慣らし保育が終わったら本格的に保育がスタートするといった感じになりますが、慣らし保育が終わった直後に気を付けたい点を知っておくと保育が安定していきます。
こどもたちが慣れてきたからと言って油断は禁物。
より細やかに保育ができるよう、ポイントをチェックしていきましょう。
スポンサーリンク
慣らし保育は新たな環境に慣れる為に必要な期間

慣らし保育はこどもたちが新たな環境に慣れる為にも必要な期間です。
無理をしてしまうとこどもに大きなストレスがかかってしまいます。
また、預けはじめは事故のリスクも高くなりますので、細心の注意が必要になります。
保護者としても保育園に預けるという生活に慣れていく必要もあります。
一方の保育園側としても、初めてお預かりするこどもの事は分からない事が多くあるでしょう。
泣いてしまっているこどもたちの保育を一生懸命行いながら、日々こどもの事を把握していくわけです。
このように慣らし保育はこどもたち、保護者、保育園(保育者)、全ての方にとって大切で必要な期間なのです。
スポンサーリンク
ポイント①予想もつかない行動に気を付ける

まずは、予想もつかない行動に気を付ける点です。
年度の後半になってくるとそれぞれのこどもの特徴や行動が分かってきますが、始まってすぐは行動が読めない事があります。
ですので、慎重に行動を見守っていきましょう。
時には予想もつかないような行動をする事があるかもしれません。
予想がつかない行動は事故や怪我のリスクを高めます。
限られた保育者の人数で対応していくわけですが、保育中気を付けて対応していくためにはお互いの声掛けや職員の位置が重要になってきます。
・××ちゃん△△しています
・私ここ見ます
何事があっても対応できるようにするには職員間の連携が不可欠です。
一人で全ての子を見るのは不可能ですし、対応ができません。
慣れてきた時こそ慎重に保育者同士声を掛け合い、お互いの配置なども確認しながら保育していきましょう。
スポンサーリンク
ポイント②保護者とのコミュニケーション
次は保護者とのコミュニケーションです。
預け初めのころは慣らし保育や仕事復帰前などで送迎時に余裕があることも多いです。
しかし、お仕事が始まり、忙しくなってくるとゆっくりとお話をする時間が取れなくなる事があります。
・家庭での様子が聞けない
・お知らせなどの伝達が伝わらない
・お互いに質問しづらくなる
上記の様に、コミュニケーションが十分でないと保育に必要な情報が得られないばかりでなく、園のことや保護者の想いなども伝わらなくなります。
特にこどもの姿が共有できなくなると家庭と保育園の連携にも関わります。
連携不足はこどもに影響が出てしまいます。
家庭と園に大きな相違があったら戸惑うのはこどもです。
少し極端な書き方になりましたが、こどもの育ちに大きな影響を与える可能性だってあるのです。
忙しいとは思いますが、欠かさず意識してコミュニケーションをとっていきましょう。
スポンサーリンク
ポイント③体調管理(大人もこどもも)

続いては体調管理です。
集団生活が初めてのこどもは免疫も弱く、風邪などをひきがちです。
毎年のように慣らし保育が終わるころに鼻水や咳、熱がでるケースが見られます。
私の園でも大体4月下旬ころ、入園後1ヶ月あたりで体調を崩す園児がでます。
そして、保育者の中でも風邪をもらってしまう方もいます。
新年度入ると環境が変わり、新入園児は大きなストレスを感じます。
保育者も慣れない新しい環境で少なからずストレスや負担を感じています。
そういった時は体調を崩しがちです。
体調に変化はないかこまめにチェックし、必要に応じて保護者、職員間で共有しましょう。
また、体調管理をするにはゆっくり休息をとるのが一番です。
・適度に運動する、外に出る
・食事をしっかりとる
・異変を感じたら早めに病院受診、薬を飲む
・ゆったりできる環境を整える
大人もこどもも体調管理の基本は同じです。
無理に登園してしまうと風邪が長引く事もあります。
仕事との兼ね合いもありますが、体調不良時はあまり無理しない様に気をつけていきましょう。
スポンサーリンク
ポイント④保育者同士の情報の共有
4つ目は保育者同士の情報の共有です。
1つ目のポイントでも書きましたが、保育中における保育者同士の連携は必要不可欠です。
加えて、保育者同士の情報の共有もすごく大事になってきます。
・保護者に関すること
・保育であった事例
・事故やヒヤリハットの共有
新年度始まってからしばらくはバタバタした日々が続きます。
他のクラスの情報を全く知らないといったケースは多くあると推察されます。
担任を持っている園児の情報を知っているのは当たり前の事ですが、保育園の職員として通っているこどもの事を知っておくのも必要な事です。
繰り返しになりますが園児に関する情報の共有は必要な事です。
意識して「周りに伝えていく」「知ろうとする」ことを意識してみましょう。
スポンサーリンク
ポイント⑤時間帯ごとの保育環境を整備する

最後は時間帯ごとの保育環境の整備です。
慣らし保育中は早いお迎えで遅くまで園児が残らないことが多いと思います。
しかし、終わる頃になれば保育時間も伸びて早朝や夕方〜夜にかけて保育することになります。
ですので、その時間帯にいるこどもに合った環境を整備していくことが必要になるのです。
特に朝、夕方は合同保育になる園もあると思います。
また、保育者の人数も全員揃っていないので、手薄な状況にもなりかねません。
その時にこどもが過ごす環境が整備されていないと事故や怪我のリスクが上がるだけでなく、安心して過ごすことができなくなります。
・どの部屋、どのスペースで過ごすのか
・どの様に時間を使っていくのか
・保育者それぞれの役割分担
環境の整備にあたり考えることは多くありますが、細かなところまで考えられるとよりこどもが安心して過ごすことができます。
また、保育時間が長くなることにより、こどもの気持ちが不安定になり泣いてしまうことも考えられます。
こどもに寄り添って保育するための環境を考えていきましょう。
スポンサーリンク
保育者同士の連携とコミュニケーションをしっかり取ろう

ここまで慣らし保育が終わった直後に気をつけたいポイントを5つ紹介しました。
どれも大事なことではありますが、個人的には特に保育者同士の連携とコミュニケーションはしっかり取るべきだと思いますし、大事なことだと思っています。
保育は人と人が関わり合う仕事。
連携やコミュニケーションを取らないと仕事としては成り立ちませんし、何よりこどもたちが安心して過ごすことができません。
慣らし保育が終わった直後はこどもも保育者も慣れてきた反面、油断しやすい時期でもあります。
繰り返しにもなりますが、慣らし保育が終わった頃の事故発生のリスクは高いです。
その時期に保育をどの様に行うかは各園保育園で様々ですが、こどもにとって不利益にならない様にするにはどうするべきか、しっかり考えていきましょう。
スポンサーリンク
*************
【読者の方へお知らせ】
この度、10年以上の園長経験を生かしたnoteをリリースいたしました!
タイトルは…
「園長歴10年以上の自信作!保育者が働きやすい保育園(職場)を作り上げる10の秘訣」
あなたの職場を働きやすい職場にするための秘訣を10個にまとめました!
園長先生や主任、リーダー保育士だけでなく、これから上の役職を目指!と思っている方にも参考になる内容となっております。
有料ではありますが、10年以上取り組んで成果があったものばかりですので、自信をもってお届けいたします。
noteの会員でXのアカウントをお持ちの方は割引になるサービスもあります。
noteをリリースいたしました!
お手に取っていただけたら嬉しいです。
この投稿をリポストするとお得に記事を読むことができます。園長歴10年以上の自信作!保育者が働きやすい保育園(職場)を作り上げる10の秘訣 | 保育士園長まゆあ @hoikushiencyo #note #保育 #保育士 https://t.co/9HkDaAo2FT
— 保育士園長まゆあ@保育者が幸せに働ける職場作りやります (@hoikushiencyo) May 12, 2024
(こちらのポストに詳細をつけています)
一つでも多くの保育園(職場)が働きやすい場所になるよう願っています!
【購入はこちら↓】